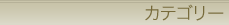ブログ個人トップ | 経営者会報 (社長ブログ)
We are Flower People の日記
- ブログトップ
- ブログ個人トップ
前ページ
次ページ
2024年05月15日(水)更新
二年ぶり、神田明神薪能
昨日の神田明神薪能は寒い夜となり、本当に冷えましたが皆さんコート持参でした。私は背広の下にベストでした。妻は軽いコートを持ってきていました。その位で丁度良い夜となりました。
今回で確か5回ほど伺っていますが、席は1列1番、2番と素晴らしくいい席を頂きました。知り合いの方が主催者の関係で席は頼みますが売れ行き次第でどこでもいいことになっています。今回のように一番前は初めてでした。お隣は紫式部ですっかり有名になった根本知さんでした。きっとおえらい方なのでしょうが、どなたが来ても普通に対応されていました。感じのいい方でした。
この日は神歌に始まり狂言の貰婿、お仕舞は杜若、お能は葵上です。
神歌は金剛流のご宗家の金剛永謹を中心に素謡形式で披露されていました。開催場所が神田明神だけに神歌は最もふさわしいものでした。今日の構成はお仕舞が「杜若」でしたがこれは時期のものとして選ばれたのでしょう。杜若のキリ(最後の数分間の部分)を舞われましたが、お持ちになっている扇子の柄は金地に杜若が描かれた見事な扇子でした。
最後の「葵上」は何といっても現在NHKの紫式部が大人気ですから選んだのだとおもいます。見どころは物の怪に取りつかれ鬼と化した葵上と呪文を唱えながら鬼を出そうとする
小聖(比叡山横川)の戦いですが、最後はついに小聖に祈り伏せられ心安らかになっていきます。シテ方とワキ方の見事な戦いの演技でした。葵上の面(般若)は目と牙が炎の明りに反射し本当に怖かったです。
神田明神という、普段は祈りの場で行なわれたお能の会は恐らく演じられた先生方はやりづらかったと思いますが、これからもぜひ続けてほしい薪能です。
今回で確か5回ほど伺っていますが、席は1列1番、2番と素晴らしくいい席を頂きました。知り合いの方が主催者の関係で席は頼みますが売れ行き次第でどこでもいいことになっています。今回のように一番前は初めてでした。お隣は紫式部ですっかり有名になった根本知さんでした。きっとおえらい方なのでしょうが、どなたが来ても普通に対応されていました。感じのいい方でした。
この日は神歌に始まり狂言の貰婿、お仕舞は杜若、お能は葵上です。
神歌は金剛流のご宗家の金剛永謹を中心に素謡形式で披露されていました。開催場所が神田明神だけに神歌は最もふさわしいものでした。今日の構成はお仕舞が「杜若」でしたがこれは時期のものとして選ばれたのでしょう。杜若のキリ(最後の数分間の部分)を舞われましたが、お持ちになっている扇子の柄は金地に杜若が描かれた見事な扇子でした。
最後の「葵上」は何といっても現在NHKの紫式部が大人気ですから選んだのだとおもいます。見どころは物の怪に取りつかれ鬼と化した葵上と呪文を唱えながら鬼を出そうとする
小聖(比叡山横川)の戦いですが、最後はついに小聖に祈り伏せられ心安らかになっていきます。シテ方とワキ方の見事な戦いの演技でした。葵上の面(般若)は目と牙が炎の明りに反射し本当に怖かったです。
神田明神という、普段は祈りの場で行なわれたお能の会は恐らく演じられた先生方はやりづらかったと思いますが、これからもぜひ続けてほしい薪能です。
2024年03月21日(木)更新
自由な想像力
お能の特徴の一つは舞台上にはほぼ何もないといったとことでしょうか。見る側の想像力が問われる舞台だともいます。今月一度歌舞伎座に参りましたが、これでもかといった具合に舞台が移り変わり、驚くほどの精巧さで舞台が作り出されます。見る側は話の筋を一層分かり易く理解することが出来ます。
その意味ではお能の場合は言葉もわかりづらく背景もないことから、余程理解している人以外お能という舞台芸術を単に見ているということになってしまいます。これらの解決策は見る回数を重ねるしか(お能千番:黙ってお能を千番見ましょう)言いようがないようです。さらに言葉が聞き取れるようになってくると今度は言葉の意味や、その場所の意味など更に理解を深めなければいけない事が次々出てきます。
私の場合、それでも出かけていくのは700年続く舞台が当時とほぼ変わらぬ姿で目の前で演じられている事実の重みです。確かに衣装は豪華になって来た様です。また演じられる時間も随分長くなったようです。舞台衣装の中には足利将軍や秀吉から賜ったものもあり、時にそれらを身に着けることもあるようです。このように、長い歴史の中で変わらず能舞台で演じられる姿そのものが貴重なことだと考えています。
私は理解を深めるために舞台に通いますが、それを補完するためにNHKの「FM能楽堂」とFM鎌倉の「お能への誘い」をよく聞きます。また、ユーチューブ等のお能は参考になることがたくさんあります。
早く舞台上の事柄が目の前に浮かぶようになりたいと考えています。
その意味ではお能の場合は言葉もわかりづらく背景もないことから、余程理解している人以外お能という舞台芸術を単に見ているということになってしまいます。これらの解決策は見る回数を重ねるしか(お能千番:黙ってお能を千番見ましょう)言いようがないようです。さらに言葉が聞き取れるようになってくると今度は言葉の意味や、その場所の意味など更に理解を深めなければいけない事が次々出てきます。
私の場合、それでも出かけていくのは700年続く舞台が当時とほぼ変わらぬ姿で目の前で演じられている事実の重みです。確かに衣装は豪華になって来た様です。また演じられる時間も随分長くなったようです。舞台衣装の中には足利将軍や秀吉から賜ったものもあり、時にそれらを身に着けることもあるようです。このように、長い歴史の中で変わらず能舞台で演じられる姿そのものが貴重なことだと考えています。
私は理解を深めるために舞台に通いますが、それを補完するためにNHKの「FM能楽堂」とFM鎌倉の「お能への誘い」をよく聞きます。また、ユーチューブ等のお能は参考になることがたくさんあります。
早く舞台上の事柄が目の前に浮かぶようになりたいと考えています。
2024年03月12日(火)更新
松竹
江戸から明治になり、各芸能関係者は大変なご苦労があったようです。お能は今まで将軍家や各大名家にお抱えの芸能として生活には困ることがなかったのですが、明治になり一気にその関係性は断たれました。
歌舞伎は将軍家とは関係のない庶民のもので、いきなり困ることはなかったようです。更に歌舞伎と文楽は松竹がスポンサーとなりビジネスとして成り立ちましたので、歌舞伎は一層発展していくことになりました。しかし文楽はかなり早い段階で松竹と関係性を断ち切られました。一人で生きていくとなると厳しいことになります。
一昨日歌舞伎座へ参りましたが、さすがに松竹です。現在の歌舞伎座は五代目の様です。設計は隈研吾氏のお仕事です。外見の重厚感と言い、大きな舞台をもつ建物は客席には柱一つなく一階席から三階席のどこに座っても舞台を見ることが出来ます。この空間が大きな外観の建物になっているのでしょう。
私は車で出かけていますが、車での来場者に対してもいい対応をしてくれます。また1時間分の無料サービス更に時間当たりも500円と銀座周辺としては安い設定になっています。
このような対応のできる歌舞伎はいいとしてもお能、文楽、自ら公演企画など行う芸能はきっとご苦労の多い事でしょう。
歌舞伎は将軍家とは関係のない庶民のもので、いきなり困ることはなかったようです。更に歌舞伎と文楽は松竹がスポンサーとなりビジネスとして成り立ちましたので、歌舞伎は一層発展していくことになりました。しかし文楽はかなり早い段階で松竹と関係性を断ち切られました。一人で生きていくとなると厳しいことになります。
一昨日歌舞伎座へ参りましたが、さすがに松竹です。現在の歌舞伎座は五代目の様です。設計は隈研吾氏のお仕事です。外見の重厚感と言い、大きな舞台をもつ建物は客席には柱一つなく一階席から三階席のどこに座っても舞台を見ることが出来ます。この空間が大きな外観の建物になっているのでしょう。
私は車で出かけていますが、車での来場者に対してもいい対応をしてくれます。また1時間分の無料サービス更に時間当たりも500円と銀座周辺としては安い設定になっています。
このような対応のできる歌舞伎はいいとしてもお能、文楽、自ら公演企画など行う芸能はきっとご苦労の多い事でしょう。
2024年02月22日(木)更新
意外に多い(?)能楽ファン
最近分かったことですが、花き業界に関係する方々の中でどうやら能楽に関心をお持ちの方が何人かおられるようです。
先週の大田花きの磯村様のコラムの中に、中学からのご友人に能役者のお子様がいらして大きくなってからそのご友人にお能を習っていると、お書きになっていました。随分前になりますが、お会いした際、舞台に興味があるとお聞きしましたが、お能の事だったのかと今初めて知りました。何十年もお続けになっていることは尊敬の対象です。
更にごく最近、矢来能楽堂の九皐会(きゅうこうかい)の定期公演に出かけているお話を親しいお取引先の方から伺いました。時間を見つけてお出かけになるのでしょうが素晴らしいと思います。矢来能楽堂は観世の特別の家柄(観世宗家の分家)の観世銕之丞家の分家となっています。観世喜之先生がご当主です。この能楽堂で金春に関係する円満井会の定期公演もこちらで開いています。一度は行きたい能楽堂です。
私もこの二、三年来友人を誘い、北浦和で行われる座敷から庭で行われる薪能を見ています。
見学者も100名足らずですが、なんとも贅沢なお能の会(半能+狂言)です。金春のシテ方の先生が毎回参加されています。20年以上続いているそうです。
先週の大田花きの磯村様のコラムの中に、中学からのご友人に能役者のお子様がいらして大きくなってからそのご友人にお能を習っていると、お書きになっていました。随分前になりますが、お会いした際、舞台に興味があるとお聞きしましたが、お能の事だったのかと今初めて知りました。何十年もお続けになっていることは尊敬の対象です。
更にごく最近、矢来能楽堂の九皐会(きゅうこうかい)の定期公演に出かけているお話を親しいお取引先の方から伺いました。時間を見つけてお出かけになるのでしょうが素晴らしいと思います。矢来能楽堂は観世の特別の家柄(観世宗家の分家)の観世銕之丞家の分家となっています。観世喜之先生がご当主です。この能楽堂で金春に関係する円満井会の定期公演もこちらで開いています。一度は行きたい能楽堂です。
私もこの二、三年来友人を誘い、北浦和で行われる座敷から庭で行われる薪能を見ています。
見学者も100名足らずですが、なんとも贅沢なお能の会(半能+狂言)です。金春のシテ方の先生が毎回参加されています。20年以上続いているそうです。
2024年02月19日(月)更新
各種芸能
昨日の日曜日は式能へ出かけていきました。
式能は現在年に一回、日本能楽協会の正式なお能の会となります。その昔(江戸時代)、将軍職を朝廷から宣下された時のような大事な時に江戸城で式能が開催されました。その意味では、当時は最も格式の高いお能の会となります。式能の式は式楽と言い徳川幕府の決めた正式な芸能です。他にも幸若舞などがありました。
お能5流派(江戸時代は四座+1流:現、喜多流)。狂言2流派全ての流派が1日で「翁」附五番立を行います。今年は観世流観世清和宗家が翁を演じました。その後、観世流、金春流、宝生流、金剛流、喜多流からそれぞれお能が演じられます。お能とは別に翁を始めに演じますが、「翁」は五穀豊穣、天下泰平を祈っての神事となります。
昨年も同じように感じましたが、翁を含めお能が6番演演じられ、更に狂言が4番演じられます。開演朝10時から終演夜7時半までの10時間近くお能を見ることになりますが、長時間になることはじめから分かっていることや番組がよく考えられ、退屈しない演目などから疲れることはありません。恐らく企画を立てる段階から相当考えられての事でしょう。
さて、芸能には今回のようなお能もありますが、大きな組織の歌舞伎や文楽などメジャーな物も有名です。しかし各地に残る芸能もたくさんあります。東大和には「清水囃」といった芸能が残っています。伝統芸能は町、村、部落の数だけ存在しています。担い手がいないことからやめていく芸能も数多くありますが、何とか継続して欲しいと思います。また、これらはその土地ではなく、東京都、NHKなどが企画を立て地域の芸能を我々に紹介しています。
小学生の頃、神楽の大好きな高校生の兄によく色々な神社に連れて行ってもらったことを思い出します。
式能は現在年に一回、日本能楽協会の正式なお能の会となります。その昔(江戸時代)、将軍職を朝廷から宣下された時のような大事な時に江戸城で式能が開催されました。その意味では、当時は最も格式の高いお能の会となります。式能の式は式楽と言い徳川幕府の決めた正式な芸能です。他にも幸若舞などがありました。
お能5流派(江戸時代は四座+1流:現、喜多流)。狂言2流派全ての流派が1日で「翁」附五番立を行います。今年は観世流観世清和宗家が翁を演じました。その後、観世流、金春流、宝生流、金剛流、喜多流からそれぞれお能が演じられます。お能とは別に翁を始めに演じますが、「翁」は五穀豊穣、天下泰平を祈っての神事となります。
昨年も同じように感じましたが、翁を含めお能が6番演演じられ、更に狂言が4番演じられます。開演朝10時から終演夜7時半までの10時間近くお能を見ることになりますが、長時間になることはじめから分かっていることや番組がよく考えられ、退屈しない演目などから疲れることはありません。恐らく企画を立てる段階から相当考えられての事でしょう。
さて、芸能には今回のようなお能もありますが、大きな組織の歌舞伎や文楽などメジャーな物も有名です。しかし各地に残る芸能もたくさんあります。東大和には「清水囃」といった芸能が残っています。伝統芸能は町、村、部落の数だけ存在しています。担い手がいないことからやめていく芸能も数多くありますが、何とか継続して欲しいと思います。また、これらはその土地ではなく、東京都、NHKなどが企画を立て地域の芸能を我々に紹介しています。
小学生の頃、神楽の大好きな高校生の兄によく色々な神社に連れて行ってもらったことを思い出します。
| «前へ | 次へ» |
- ご挨拶(9)
- その他(6)
- ガーデン・植物、花(24)
- チャコボール(3)
- ビジネス(6)
- ピーターラビット™フラワーズ(1)
- 企業情報(23)
- 商品・デザイン(29)
- 地元・地域(34)
- 夢・経営理念(9)
- 季節(6)
- 季節・趣味(12)
- 安全管理(1)
- 家族・交友(14)
- 展示会(17)
- 店舗紹介・グルメ(2)
- 思い出(3)
- 技術(7)
- 新着商品・サービス(8)
- 日常(84)
- 書籍(3)
- 未来(11)
- 歴史(1)
- 気候(7)
- 決意(11)
- 海外情報(9)
- 石川県(6)
- 社会(4)
- 社会情勢・業界情報等(51)
- 能登(1)
- 能登事業所(18)
- 自然(3)
- 興味・関心(16)
- 花の業界情報(91)
- 親交(58)
- 趣味(53)
- 趣味・ゲーム(1)
- 関心・技術(35)
 ログイン
ログイン